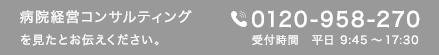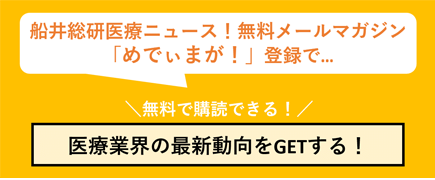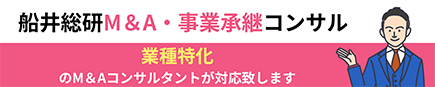【診療報酬改定2026】国の考えは…?
- コラムテーマ:
- 経営計画/経営管理 業界動向 コロナ対策 クリニック・医院開業 診療報酬改定 事業承継 研究会 内科 糖尿病内科 循環器内科 呼吸器内科 訪問リハビリ 美容医療 在宅医療 自由診療 管理栄養士 webマーケティング Google広告 集患・ホームページ活用 Googleマップ 院内マーケティング IT活用 web問診 web予約 診療効率化 シュライバー/クラーク スタッフマネジメント リーダーミーティング スタッフ定着率 スタッフ自律型組織 スタッフミーティング 採用 教育 健康診断/検診 企業健診/雇入れ健診 定期検診 特定疾患療養管理料 慢性疾患 睡眠時無呼吸症候群 評価制度 診療見学 従業員満足度調査 接遇 SEO対策
Table of Contents
気がつけば、今年も残すところ約3か月となり、年末が意識される時期になりました。
そして来る2026年、偶数年といえば診療報酬改定の年です。
これまでの診療報酬改定を見ても、
”国が推進していきたいことに報酬をのせていくこと”は明らかです。
では、国の推進したいものとは…?
【医療DX】
医療DXは、今回の改定でも重要なキーワードになりそうです。
その狙いは単なるデジタル化ではなく、
”医療情報をつなぎ、業務の効率化と医療の質向上を両立させること”
にあります。
国はすでに「全国医療情報プラットフォーム構想」を掲げ、
・電子カルテの標準化
・マイナ保険証を用いたオンライン資格確認
・電子処方箋の運用拡大
・PHR(Personal Health Record:個人健康情報)の活用
といった取り組みを進めています。
たとえば、
紹介・逆紹介のスムーズ化、検査データの共有、重複処方の減少…など
日常診療の中でもメリットが生まれると考えられます。
医療DXは「国の方針だからやる」ではなく、
現場の働きやすさと患者対応力を高めるためのツールとして
状況に応じて、検討していただくことが重要と考えています。
【医療従事者の賃上げ】
物価高は依然として続いており、2025年中小企業の
おおよそ6,7割が賃上げ予定とされていました。
そのような背景で、医療従事者においてもベースアップの流れは議論が続いています。
日本全体では少子高齢化が進み、医療のニーズが高い高齢者が増える一方で、
医療の供給側である医療従事者は減少しています。
そのため、国としては前述の医療DXを活用し、
限られた人員でも質の高い医療を提供できる
「高生産性の医療体制」を目指しています。
【地域の患者さんとの最初の接点となる「かかりつけ医」】
「外来機能の分化」と「かかりつけ医機能の制度化」もトピックに上がっています。
病院の外来には軽症の患者さんが多く、
専門治療が必要な患者さんが診察してもらうまでに
時間がかかっているという現状があります。
こうした課題を解決するために、
・大病院は高度・専門医療に集中する
・診療所は地域のかかりつけ医として身近な外来を担う——
という明確な役割分担が進められています(外来機能の分化)
また、かかりつけ医は”地域包括ケアの入り口”
としても重要な役割があります。
※地域包括ケア=高齢者を医療・介護・生活サポートで地域によって支援する構想
【一方で、医療費は抑制したい】
一方で、財務省では医療費の増加を抑えたいという姿勢が見られます。
検討中のOTC類似薬品の保険適用除外や、医療DXによる情報共有で
検査や処方の重複を防ぐ仕組みは、その流れの一環です。
これからの診療報酬改定を踏まえて、どう動けばいい?
大切なのは、国の方針を正しく理解したうえで、
「先生ご自身が理想とする医療をどのように実現していくか」
だと考えています。
診療報酬改定はあくまで“国の方向を示す指標”です。
それを基にどのように舵をとるかは、先生方次第です。
今後も判明次第、より具体的な内容を随時ご案内差し上げてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
少しでも日々のヒントになれば幸いです。
同じテーマで記事を探す
- 経営計画/経営管理
- 業界動向
- コロナ対策
- クリニック・医院開業
- 診療報酬改定
- 事業承継
- 研究会
- 内科
- 糖尿病内科
- 循環器内科
- 呼吸器内科
- 訪問リハビリ
- 美容医療
- 在宅医療
- 自由診療
- 管理栄養士
- webマーケティング
- Google広告
- 集患・ホームページ活用
- Googleマップ
- 院内マーケティング
- IT活用
- web問診
- web予約
- 診療効率化
- シュライバー/クラーク
- スタッフマネジメント
- リーダーミーティング
- スタッフ定着率
- スタッフ自律型組織
- スタッフミーティング
- 採用
- 教育
- 健康診断/検診
- 企業健診/雇入れ健診
- 定期検診
- 特定疾患療養管理料
- 慢性疾患
- 睡眠時無呼吸症候群
- 評価制度
- 診療見学
- 従業員満足度調査
- 接遇
- SEO対策
この記事を書いたコンサルタント

佐野 徹
慶應義塾大学商学部 卒業。
新卒で船井総合研究所に入社。
大学では経営学を専攻し、人オペレーションにおける最適配置について学んでおり、効率化を目的としたオペレーション改革を得意としている。
入社以来、医療クリニックのコンサルティングに従事し、クリニックが抱える問題の解決に取り組んでいる。