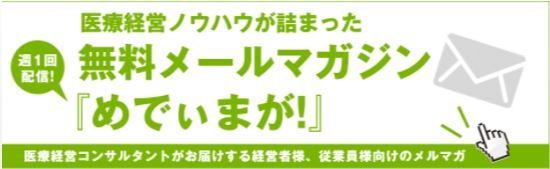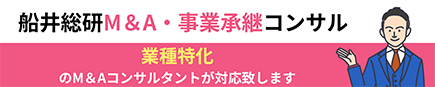Table of Contents
2026年度診療報酬改定に向けた議論が本格化しています。
今回の改定は、単なる点数の調整に留まらず、近年の物価高騰・人件費上昇という厳しい経営環境に加え、医療DXの加速、高齢化社会の進展が複雑に絡み合っています。
本コラムでは、先生方のクリニック経営に直結する3つの最重要ポイントに絞り込み解説します。
賃上げとコスト高騰への対応:「ベースアップ評価料」はどう変わる?
近年、他の産業と比較して医療従事者の賃金水準の低さが問題視されており、人材流出リスクの防止と質の高い医療提供体制の維持のため、ベースアップ(賃金水準の向上)は不可欠となっています。
さらに、物価や人件費が急激に上がっていることで、医療機関の経営は大変厳しくなっています。2026年の改定では、こうしたコスト増にどう対応していくかが、最大のポイントの一つになりそうです。
●改定の背景と目的:
◦人材確保と流出防止: 医療従事者の賃金水準を向上させ、流出を防ぎ、安定的な人材確保を目指します。
◦安定化と良質な医療提供: 診療報酬の引き上げを通じて医療機関の経営を安定させ、結果として患者さんへ良質な医療を提供し続けることを目的とします。
●「ベースアップ評価料」の方向性:
◦対象職種の拡大要望: 現在の評価料の対象職種は限定的ですが、看護補助者だけでなく事務職員など、他の職員も対象に加えるべきという要望が出ています。
◦事務負担の軽減: 届け出手続きの煩雑さが、評価料の取得を妨げる要因となっています。より多くの医療機関が取得できるよう、手続きの簡素化が求められる見込みです。
【クリニックが今すぐ取るべき対策】
改定内容に関わらず、まずは自院のコスト構造を正確に把握し、将来的な賃上げを見据えた財務計画を立てましょう。評価料の対象職種が拡大されれば、事務部門も含めた人材戦略の見直しが不可欠になります。
医療DXの加速:「加算」は「標準」へ移行する
2026年度改定は、政府が掲げる「医療DX令和ビジョン2030」に基づく中長期的な戦略の重要なステップです。全国医療情報プラットフォーム、電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定DXの3つの柱を中心に、デジタル化を加速させるための評価体系が整えられます。
●改定の背景と目的:
◦情報基盤の整備: 医療提供体制の大改革と連動し、DXを通じて地域医療構想や医師偏在対策なども進め、効率的で質の高い医療提供体制を構築します。
●DX関連加算の方向性:
◦「医療DX推進体制整備加算」の要件強化: 2024年度改定で新設されたこの加算は、マイナンバー保険証の利用率基準が2025年10月、そして2026年3月と段階的に引き上げられることが決まっています。
◦オンライン資格確認の体制整備はもはや「任意」ではなく、すべての医療機関に求められる「標準装備」として、強く求められるようになります。
【クリニックが今すぐ取るべき対策】
「DXは面倒」という認識を捨て、マイナ保険証の利用促進策を徹底しましょう。ポスター掲示だけでなく、患者さんへの丁寧な声かけなど、現場レベルでの取り組みが重要です。また、今後の電子カルテ標準化や情報共有サービスの動向を注視し、デジタル化への先行投資を検討することが、将来的な経営効率と地域連携の基盤を築きます。
生活習慣病管理・在宅医療の強化:地域包括ケアシステムの深化
高齢化の進展と国の「地域包括ケアシステム」の深化に伴い、入院医療から在宅・外来医療へのシフトは不可逆的な流れとなっています。2026年改定では、この流れを後押しし、かかりつけ医機能と在宅での医療提供を強化するための評価が焦点となります。
●改定の背景と目的:
◦地域完結型医療の推進: 病院の機能を急性期に集中させ、慢性期疾患の管理や終末期医療を地域(クリニック・在宅)で担う体制を強化します。
◦在宅医療の適正化:
在宅医療のニーズは増加していますが、医療費は主に「回数の増加」によって伸びている実態があります。このため、単なる回数増ではなく、質の高い在宅医療の提供や「不適切な在宅医療の是正」を目指した評価が検討される見込みです。
◦生活習慣病管理の見直し:
2024年改定で「生活習慣病管理料」がIとIIに分かれ、包括範囲や算定要件が大きく見直されました。2026年改定では、この見直しの影響を検証し、医療資源投入量や成果に応じた評価へと再調整される可能性があります。
●議論の具体的な方向性:
◦生活習慣病管理料の再々調整: 患者さんの病態(検査頻度など)に応じた細かな評価や、疾患コントロールが良好な患者への評価方法が再検討されます。
◦かかりつけ医機能の多段階評価:
地域包括診療料・加算について、対象疾患数の拡大や、抱える疾患数などに応じた多段階の点数設定を求める提言が出ています。これにより、地域医療を担うクリニックが算定しやすくなる可能性があります。
【クリニックが今すぐ取るべき対策】
生活習慣病患者に対しては、単に投薬するだけでなく、療養計画書に基づいた継続的な生活指導や重症化予防への介入を徹底が必要となります。また、在宅医療に取り組む場合、単に訪問回数を増やすのではなく、多職種(訪問看護、介護事業所など)との連携を強化し、質の高い地域包括ケアを提供できる体制づくりを進めることが、将来的に高い評価を得るための鍵となります。
先生方へ:「待つ」のではなく「仕掛ける」改定対応を
2026年度診療報酬改定は、物価高騰・人件費上昇というコスト増の圧力の中で、クリニックの経営が大きく左右されるものです。
持続可能な経営を実現するためには、以下の3つの重要課題に、今すぐ「仕掛けの姿勢」で取り組むことが不可欠です。
1.賃上げ・コスト対応: ベースアップ評価料の動向を注視し、事務職員を含めた人件費への対応と、コスト増を上回る収益構造を確立すること。
人件費増分を吸収するため、「単価アップ」と「業務効率化」で収益力を高めます。
・内視鏡検査数を増やす →単価アップ
・事務職員への賃上げも視野に入れ、ベースアップ評価料を取得しながら、一人当たりの生産性を上げる→単価アップ
・同じ診療時間内でより多くの検査・診察が出来るようにする→効率化
2.医療DXの加速: オンライン資格確認の体制整備はもはや必須の「標準装備」です。これを機に、DXを業務効率化と地域連携の基盤として活用すること。
DXを「待ち時間削減」と「検査の質向上」に直結させます。
・患者情報のデジタル共有(全国医療情報プラットフォーム)を活用し、紹介元・連携病院とのスムーズな情報連携を実現する。
・WEB問診や予約システムを活用し、看護師・事務スタッフが対応する業務を軽減する。資格に応じた仕事に注力できるように。
3.地域包括ケアの深化: 生活習慣病管理や在宅医療において、「質の高い管理」と多職種連携を強化し、メリハリの効いた評価に対応できる体制を整えること。
内視鏡検査の「専門クリニック」という機能に留まらず、「地域のかかりつけ医」としての機能も強化し、慢性期管理の評価を獲得します。
・消化器疾患をお持ちの患者さんに対し、生活習慣病管理料や地域包括診療料など、「継続的な管理」を適切に算定できる体制を整える。
・消化器疾患の重症化予防(特にがん予防)を通じて、地域の健康管理の中核を担い、多職種連携を強化する。
改定の議論は今後も続きます。ぜひ、この3つの波に乗り遅れないよう、最新の情報をチェックし、2026年改定を増収・成長のチャンスに変えるための戦略的な準備を進めていきましょう。
皆様の医院では、2026年度診療報酬改定の対応体制は整っていますでしょうか。
コスト増への対策、DXの推進、地域連携の強化など、算定方法の仕組みづくりや、戦略的な経営体制の構築にご関心のある方は、ぜひ一度ご相談ください。今、具体的な行動を始めることが、貴院の2年後、5年後の成長を決めます。
同じテーマで記事を探す
この記事を書いたコンサルタント

津田真里亜
大学卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。
大学では開発経済学を専門とし、途上国で暮らされている方々のことを学ぶ中で、地域社会における医療の役割の重要性を知り、医療を通じた社会貢献をしたい想いを持つ。
医療コンサルティングを通して一人でも多くの患者様へ医療を届けるために、心療内科を中心に、内視鏡内科・歯科・耳鼻科・整形外科と幅広い領域のコンサルティングを行っている。また経営者に寄り添うことを大切にし、長期的な目線で経営コンサルティングを行うことを心がけている。