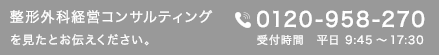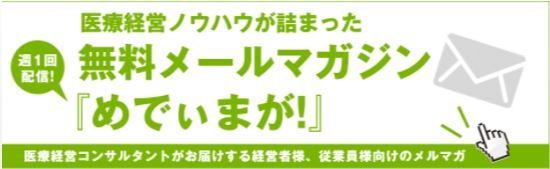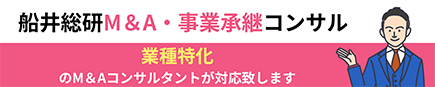Table of Contents
いつもめでぃまがをお読みいただきありがとうございます。
株式会社船井総合研究所の能美です。
「うちのPTは頑張っていて、稼働率も高いし、
きっとPT1人当たりの売上(以下、生産性)は高いはず…」
実は「稼働率が高い=PT1人当たりの売上が高い」とはならない可能性があります。
弊社では、PT1人当たり100万円/月(再診料抜き)を一つの「生産性が高い」の基準としておりますが、先生のクリニックではいかがでしょうか?
もし、これに満たない場合、改善の余地は大いにあります。
そこで、今回のコラムではこの数値の算出方法と、リハビリ室の生産性を飛躍的に向上させるための方法を、実際の成功事例を交えながらご紹介いたします。
【リハビリ室の生産性が高い状態とは】
冒頭で、リハビリの高い生産性の基準として、PT1人当たり売上を月間100万円(再診料抜き) とお伝えいたしました。
では、この100万円という目標を達成するためのシミュレーションをしてみます。
運リハⅠ185点 × 400単位 =74,000点
リハビリテーション総合実施計画書評価料 300点 × 担当患者数 100人 = 30,000点
(74,000点 + 30,000点)×10円/点 = 1,040,000円
となり、月間100万円の目標を達成することができます。
最大限、単位数を取得することは大前提であり、
それに加えてリハビリテーション総合実施計画書評価料をどれだけ算定できるか、も重要になってきますが、
ここが抜け落ちてしまっているリハビリ数値管理がよく見受けられます。
「単位はとれているけど、計画書の算定枚数の管理は抜けているかも、、、」という先生方はぜひこの機会に見直しをしてみてください!
【100万円/月の事例紹介】
「100万円/月は可能なのか?」と疑問に持たれる先生方もいらっしゃるかと存じますが、
ずばり可能です。
弊社のご支援先の事例をご紹介いたします。
以下のデータは1人当たり100万円/月を達成されたクリニック様のデータになります。
(診療日数20日換算)
【達成前】PT4名
1人あたり平均取得単位数:364単位
1人当たり計画書算定枚数:20枚
1人あたり平均売上:¥742,400円
【達成後】PT6名
1人あたり平均取得単位数:398単位
1人当たり計画書算定枚数:94枚
1人あたり平均売上:¥1,018,340円
このクリニック様では、平均取得単位数が360単位と決して低い値ではないにもかかわらず、生産性は74万円/月と伸び悩んでいました。その主な原因は、計画書の算定枚数が少ないことにありました。
そのため、このクリニック様では計画書の算定枚数を伸ばすために、
・リハビリの新患数や実患者数など計画書の算定枚数に関わる数値の管理
・2単位制から1単位制への移行
に取り組まれました。
その結果、生産性が飛躍的に向上し、100万円/月を達成することができました。
このように「生産性が高いリハビリ室」になるためには、取得単位数を最大限取得することは基本ですが、計画書の算定枚数もPT1人当たりの生産性を上げていくためには非常に重要な指標となります。
「もっと具体的に何をすればいいのか知りたい!」
「うちのリハビリ室の生産性もあげたい!」
そんな先生方のために以下のセミナーをご用意しました。
95%稼働率を実現する運動器リハビリ強化セミナー
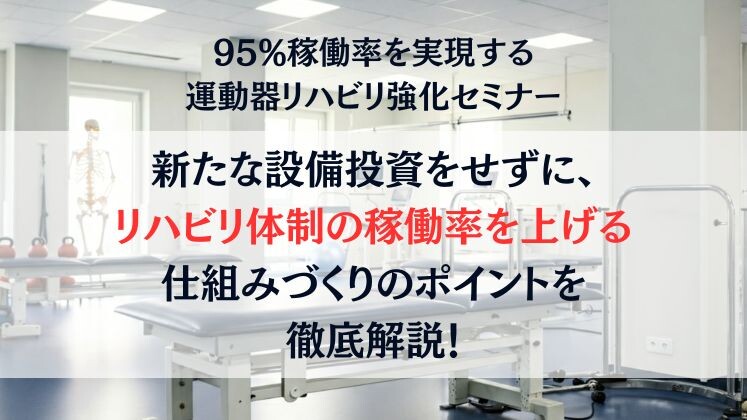
本セミナーでは、整形外科クリニックの運動器リハビリの稼働率95%、PT5人の年間売上6,000万を実現するためのポイントについて解説します。また、運動器リハビリの基本数値の管理、目標数値の設定、新患/初診を増やす集患対策など、高生産性を実現するリハビリ室運営の具体的な方法をご紹介いたします。
◆下記に当てはまる先生方はぜひご参加ください!
☑運動器リハビリの生産性を上げる取り組みについて知りたい
☑PT増員により運動器リハビリを拡大し、クリニックの業績を上げていきたい
☑高生産性の運動器リハビリを実現しているクリニックの運営ノウハウについて知りたい
☑キャンセル・空き枠を減らし、運動器リハビリの稼働率を上げていきたい
☑運動器リハビリを運営するための数値管理の方法や目標数値を知りたい
◆開催日程
1日目:2025/4/19 (土) 16:00~17:30 オンライン開催
2日目:2025/4/20 (日) 10:00~11:30 オンライン開催
3日目:2025/4/26 (土) 16:00~17:30 オンライン開催
4日目:2025/4/27 (日) 10:00~11:30 オンライン開催
この記事を書いたコンサルタント

能美元太郎
慶應義塾大学法学部を卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。入社後は医療業界のコンサルティングに従事しており、その中でも整形外科クリニックに対するコンサルティングを専門としている。医療業界のコンサルティングを通じて1人でもケガや病気に苦しむ人を減らすことをミッションにコンサルティングに従事している。また、医師の家庭に育った経験から医師の先生方の想いに寄り添そったコンサルティングを得意としている。