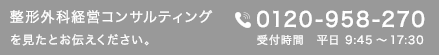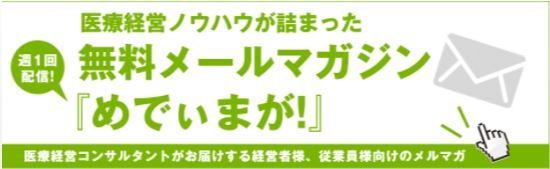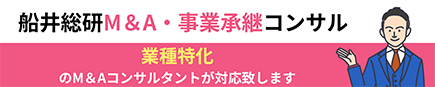こんにちは。
船井総合研究所の野中達裕です。
今回は
「通所リハビリテーションの運営方法」に関してお話させていただきます。
通所リハビリの運営方法がイメージつきにくくて取り組めていないということを耳にします。
通所リハビリの運営で目標とすべきは、
①利用者が改善する
②集客が安定し、利益がでつづける
という2点です。
それぞれにつながる効果的な運営方法について、5つのステップで紹介させていただきます。
ステップ①
「 通所リハビリテーション専任のPTを一人つける 」
通所を始めるタイミングは、保険のリハビリテーションがうまく軌道に乗ってきて
収入的に安定してからが好ましいとお伝えさせていただくことが多い理由の一つに
「 専任化するため 」という理由があります。
一般的に兼任するクリニックが多いですが
そのようなクリニックではうまくいきにくい場合が多いです。
理由は単純で、兼任だと忙しすぎて通所リハビリテーションの為にすべきことのすべてをやりきれないからです。
そのために、まず通所リハビリテーションをうまくいかせるために、主任として専任を一人つける事が重要です。
ステップ②
「 クリニックに合わせたプログラムを構築する 」
(稼働可能な人員)×(利用契約者数)によって最適な運営プログラムを検討します。
提案しているプログラムは3パターンあります。
Ⅰ、個別訓練重視型(個別20分 + 自主トレ60分)
・PT一人が4人の個別リハを順番に回し、他の時間は自主トレを行う
人員:PT1人
利用者人数:4名
メリット:オペレーションがシンプル
デメリット:受け入れられる人数が少ない
Ⅱ、集団・個別MIX型(集団20分 + 個別×自主トレ60分)
・集団プログラムを全員で行い、その後個別プログラムと自主トレに分けて行う
人員:PT1人・リハ助手2人
利用者人数:10名
メリット:同時に受け入れられる人数が増え、収支的に良い
デメリット:集団のみ受ける人と集団も個別も受ける人が出てくる
Ⅲ、グループ分離型(集団×マシンリハ40分 + 物療40分)
・2グループに分けて、[ 集団+マシンリハ ] ⇔ [ 物療 ] を回す
人員:PT1人・リハ助手2人
利用者人数:10名
メリット:同時に受け入れる人数も増え、PTの関わる時間も減り、収支的に良い
デメリット:リハ助手の教育が必要となり、利用者もある程度理解が必要になる
ステップ③
「 リハビリ助手の活躍 」
通所リハビリのキモはやはりPTによる、個別評価と施術です。
満足度を上げるためにはPTがより多くの施術を行う必要があるため
PTにはPTにしかできない業務に専念して
それ以外は全てリハビリ助手などが担うことで
より利用者さんの満足度を上げ
なおかつ多くの利用者さんを受け入れられます。
具体的には、集団体操や物療・自主トレの管理をリハ助手が行えるように指導します。
その結果、より多くの方へ個別のリハビリの提供が行えるようになります。
無資格の方でも、少し始動すれば充分担うことが出来ますので、ぜひトライしてください。
ステップ④
「 とるべき加算をおさえる 」
今回の改定でもそうですが、今後も基本報酬は増やさずに、加算で評価をする流れが加速します。
要は、「良い取り組みをやっていれば評価され、報酬に反映する」ということです。
そこで、ぜひ取得すべきべきオススメの加算というのが、下記になります。
・リハビリテーションマネジメント加算(要介護の場合は3を目標)
・事業所評価加算
・社会参加支援加算
詳細な説明は省略しますが、これらを実現するには、少ない人数ギリギリで回すのではなく、先ほど述べたような効果的な人員配置が必要です。
ステップ⑤
「 “利用者の満足度を上げるには?“をテーマに毎月ミーティングを行う 」
ステップ④までを行っていただくと運営はできるようになりますが
今後同じ運営方法で進めていくとどこかで利用者から不満が出ます。
そういった不満を持たれないために
定期的にミーティングを行い、さらに良くする方法を常に考え実行していくことで
利用者の視点での運営もできるようになり
非常に満足度の高い通所リハビリテーションを提供し続けられます。
時にはアンケートを取るなりして現状把握をすることもよいかもしれません。
以上が通所リハビリテーションの運営方法となります。
このような運営方法をおこなっていただき
今後の医院経営に役立てていただければ幸いです。
▼整形外科に特化した経営ノウハウ無料レポートはこちらから
https://byoin-clinic-keiei.funaisoken.co.jp/fairing/booklets_download/report_fairing/
こちらのレポートは全て無料でダウンロードいただけます。
すぐに実践可能な内容が盛りだくさんのレポートとなっているので、是非ご参考にしてください。
船井総合研究所
医療支援部
野中達裕
同じテーマで記事を探す
この記事を書いたコンサルタント

野中 達裕
早稲田大学を卒業。船井総合研究所に入社。看護師、理学療法士、放射線技師、医療事務などの専門職採用に注力し、小規模から大規模の法人の採用まで規模に合わせた幅広く実績を持つ。また、現場での勤務経験を活かし、医療現場の生産性向上のための診療効率化に対する提案に定評がある。