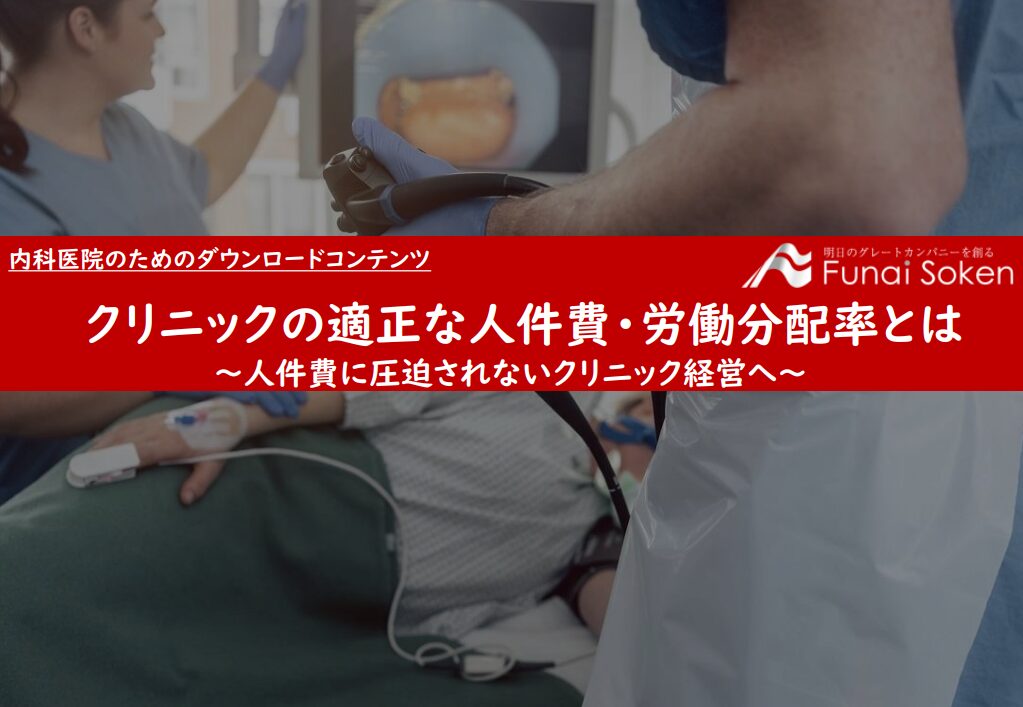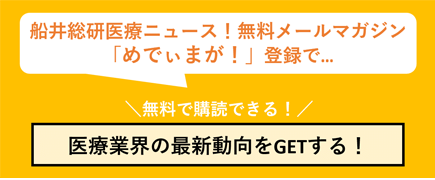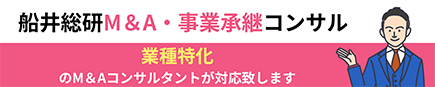人件費で悩む院長へ。労働分配率を改善し、クリニック経営を安定させる方法|内科経営
Table of Contents
なぜ今、人件費・労働分配率の適正化が重要なのか?
株式会社船井総合研究所の箱守でございます。
「長年勤務の職員の給与が年々上がっていくことに不安を感じている…」
「業績が横ばいになり、膨らみ過ぎた人件費が経営を日々圧迫している…」
「今後の新人スタッフへの給与をどうすべきか悩んでいる…」
「給与の適切な決め方が分からない、相場かどうかも分からない…」
クリニックを経営されている先生方、
このようなお悩みを感じていらっしゃいませんでしょうか?
「なんとかしたい」と思いつつも、現状の経営状況に不安を感じ、
なかなか踏み出せないでいらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。
もし、上記のような課題に一つでも心当たりがあるようでしたら、
それは、貴院の経営状況を人件費と労働分配率の観点から見直すタイミングかもしれません。
本コラムでは、人件費や労働分配率の観点から
経営状況を見直すための方法をお伝えいたします。
なぜ今、人件費・労働分配率の適正化が重要なのか?
人件費は、クリニック経営において大きな割合を占める固定費の一つです。
長年勤務する職員の給与が年々上昇し、
一方で業績が横ばいの場合、
人件費が経営を圧迫する大きな要因となります。
そこで、ぜひご検討いただきたいのが、
「付加価値・人件費・労働分配率という3つの経営指標を活用した、
人件費に圧迫されない経営」です。
これらの指標をうまく活用することで、自院の経営状況を正確に把握し、
適切な人件費管理を実現することが大切です。
人件費に圧迫されない経営を実現するには
まず、貴院の経営状況を客観的に把握し、具体的な改善策を見つける第一歩として、
以下の3つの指標を正確に理解し、活用することが重要です。
①付加価値(限界利益)
企業が事業活動によって生み出した価値を数値で表したものであり、
計算式は「売上高-変動費(原価)」になります。
※変動費:薬剤費、検査費、外注費など
この指標を把握することで、貴院が事業活動によって
どれだけの価値を生み出しているかを客観的に評価し、
利益を確保するための基準を理解できます。
この付加価値が固定費(人件費含む)を賄いきれない場合、経営は赤字に陥ります。
②人件費
給与手当、福利厚生費、法定福利費、退職金、役員報酬などが含まれます。
人件費は固定費の一つであり、
一度上がると下げるのが難しい特性があります。
しかし、評価制度や賃金体系など、
給与手当の仕組みを適切に整えることで、
その水準を戦略的にコントロールし、
モチベーションを維持しながら適正化を図ることが可能です。
③労働分配率
労働分配率は「人件費÷付加価値」で算出され、
付加価値のうちどの程度が人件費に配分されているかを示す指標です。
労働分配率が高い場合、その主な原因は以下のいずれか、または両方が考えられます。
・分子である人件費が大きい状態
:「給与水準が高すぎる(業界相場と比較して過剰に支給している可能性)」
・分母である付加価値が小さい状態
:「医業収入が低い(付加価値を生み出す体制を見直す必要性がある)」
事業形態(個人事業主や医療法人)や標榜科目によって労働分配率は様々ですが、
自院の規模や診療科、経営目標に合わせた適正値を見つけることが重要です。
これら3つの経営指標を基に、税理士の方とも連携しながら自院の状況を把握し、
目指す利益から逆算して労働分配率を適切に管理・調整していきましょう。
人件費を抑える仕組みの導入に加え、
売上、つまり付加価値額を増やすことで、労働分配率を最適化することが可能になります。
付加価値額を増やすためには、
1人のスタッフが1時間あたりにどれだけの付加価値を生み出しているかを示す
人時生産性のアップが不可欠です。
人時生産性が高まることで、少ない人員でより多くの価値を生み出せるようになり、
結果として労働分配率の改善につながります。
そのためには、貴院に合った集患戦略を練り、
診療効率化の仕組みを構築し、スタッフのスキルアップを図ることが大切です。
固定費の見直しや最適化策を検討し、同時に付加価値額の増額を目指すことこそが、
人件費に悩まされない盤石な経営への道となります。
本コラムでは、人件費・労働分配率について解説しました。
本コラムを読んで
「自分のクリニックはどうだろう?」「具体的な改善策を知りたい」
と感じられたなら、ぜひ一度、無料経営相談をご活用ください。
弊社では、経営戦略から集患、効率化、採用などの具体的な施策まで、
クリニック経営における様々なテーマでサポートしております。
貴院のお悩みに合わせ、最適な解決策をご提案いたします。
クリニックの適正な人件費・労働分配率とは~人件費に圧迫されないクリニック経営へ~