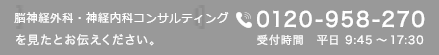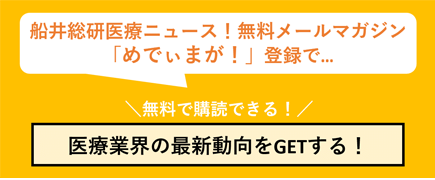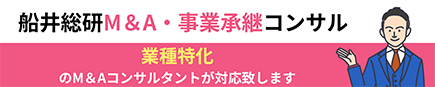【Web集患】アクセスを稼ぐだけでは不十分!来院につながる分析とは
Table of Contents
患者数を増やすために、日々、診療の合間を縫って、
ホームページの改善や情報発信に力を入れている先生も多いのではないでしょうか。
しかし、
「頑張ってホームページ対策をしているのに、なかなか新患数が増えてこない…」
「ホームページのアクセス数は増えているが、予約につながっていない…」
と、お悩みではないでしょうか。
ホームページのアクセス数が増えても、
必ずしも集患対策として十分だとは言い切れないのです。
大切なのは、「誰が」「どのページを」見ているのか、
そして「そこからどれだけ来院に繋がっているか」なのです。
「来院につながる」ホームページにするために
Web経由からの新患数を増やすためには、
ホームページのアクセス数を増やす事はとても大切です。
アクセス数を把握していない方は、
まずこのアクセス数を確認してみてください。
今回は、さらにアクセス数の「その先」を見る視点についてお伝えします。
アクセス数を増加傾向にあっても、
そのアクセスが、単なる情報収集目的のアクセスなのか、
「クリニックの受診を検討している」方のアクセスなのか、
それとも「このクリニックを受診したい」という意思を持ったアクセスなのかは、
アクセス数だけでは判断できません。
重要なのは、診療圏内のユーザーがホームページを見ているか、
そして、実際に予約や来院に繋がるページ
(例:初診予約ページ、診療案内ページ、アクセス情報)
がどれだけ閲覧されているかです。
症状の解説や治療法の情報提供はもちろん大切ですが、
来院に結びつく「次の一歩」を促す導線が、
ホームページ上で明確になっているしょうか?
集患力アップのためのホームページ分析
来院につながるホームページ対策を考えるためには、
以下のことを調べてみてください。
・人気ページランキング: どのページが一番見られているか
・ユーザーの地域情報: クリニックの商圏内からのアクセスがどれくらいあるか。
・コンバージョン経路: どのページから「予約ページ」「アクセス情報ページ」などに遷移しているかを確認する。
※コンバージョン:ウェブサイトなどで設定した目標が達成されること
⇒ここでは、来院につながるページに遷移する事
これらのデータから、
来院数を増やすためのアクションを考えることが大切です。
例えば、
ホームページ全体のアクセス数に対して、
予約ページにたどり着いた方が何人いらっしゃるか。
ここに、集患を最大化するヒントが隠されています。
また、実際の予約が入っている数や
来院された新患数も照らし合わせて、費用対効果を確認してみてください。
「ホームページからの集患を加速させたい」
そうお考えでしたら、ぜひ具体的な施策を検討してみませんか?
船井総研では、
貴院のホームページが「患者さんの来院に繋がる」ための具体的な改善策など
集患対策をお伝えするセミナーを開催いたします。
今回のセミナーでは、アクセス解析の具体的な見方から、
患者さんの行動を促すためのコンテンツ作り、
そして予約・来院へ導くためのホームページ戦略まで、成功事例を交えながら詳しく解説します。
きっと、貴院の集患における次のヒントが見つかるはずです。
多忙な院長先生にこそご参加いただきたい内容です。
【セミナー名】
脳神経クリニック向けMRI400件突破するための集患セミナー
【日程】
2025年12月13日 (土)16:00~17:30 (オンライン)
2025年12月14日 (日)10:00~11:30 (オンライン)
2025年12月20日 (土)16:00~17:30 (オンライン)
2025年12月21日 (日)10:00~11:30 (オンライン)
【お申込みは以下のページから】
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/133037
脳神経クリニック向けMRI400件突破するための集患セミナー
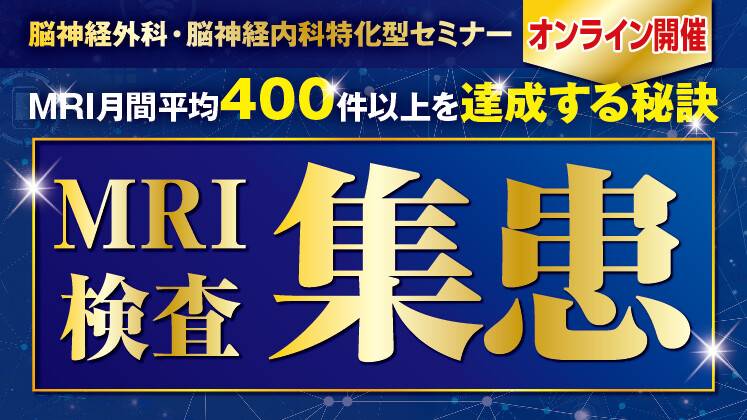
本セミナーは、脳神経外科クリニックがMRIの稼働率を向上させ、MRI1台で月間400件超えの撮影を実現するための、集患の秘訣を徹底解説します。
MRIの稼働率を最大化するための具体的な集患方法、競合クリニックの増加に対応する戦略、Webマーケティングによる仕組みづくりなどについて、成功事例を交えながら学ぶことができます。
MRIの撮影件数が伸び悩んでおり、クリニックの業績を向上させたい経営者の方におすすめのセミナーです。
同じテーマで記事を探す
この記事を書いたコンサルタント

今 勝彦
札幌医科大学を卒業後、作業療法士として、急性期~回復期脳神経外科病で勤務。
現場での臨床や指導経験に加え、大学院での研究、学会発表等幅広い経験を持つ。
船井総研入社後は、臨床経験をもとにした業績向上、医療の質向上のために、運動器リハビリの立ち上げ、集患対策、マネジメントなど様々なコンサルティングを実施している。