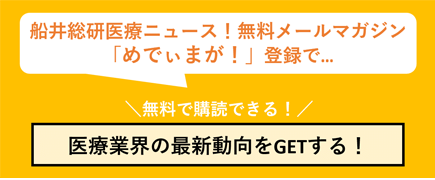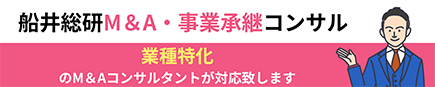医療法人社団ときわ

医療法人社団ときわ 理事長
医療法人社団ときわ
赤羽在宅クリニック 院長 小畑 正孝 氏
本日は、在宅医療を提供する「医療法人社団
ときわ 」の設立経緯から組織運営、今後の展望
について 、 医療法人社団ときわ 理事長 小畑様 にお話を伺いました。在宅医療への熱い想いと、革新的な取り組みについてインタビュー形式でお届けします。
【医療法人
社団 ときわ 沿革 】
・2016年9月 赤羽在宅クリニック 開業
・2017年7月 大宮在宅クリニック 開業
・2017年8月 医療法人社団ときわ 設立
・2018年7月 医療法人社団ときわ 練馬在宅クリニック 開業
・2019年1月 ときわ在宅クリニック墨田 開業
・2021年5月 サルスクリニック武蔵境 開業
・2021年6月 サルスクリニック日本橋 開業
・2022年11月 サルスクリニック有明 開業
・2025年4月 医療法人社団ときわ 赤羽在宅クリニックは特定非営利活動法人日本緩和医療学会「日本緩和医療学会基幹施設」に認定

写真:サルスクリニック 有明
クリニック(法人の)概要について
船井総研:
本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。早速ですが、 ホームページでは患者数が 6,000 人を超えていると拝見しました。これは累計の患者数でしょうか?
また、 現在診察されている訪問 患者数と、居宅と施設それぞれの内訳について教えていただけますか?
小畑様:
はい、ホームページに記載している 6,000 人超という数字は、これまでの累計患者数になります。現在アクティブに診療させていただいている患者さんは、 2025 年 6 月末時点で 1,525 人です。内訳としては、居宅が約 45% 、設が約 45% 、そして小児が約 10% となっています。
船井総研:
居宅と施設の患者さんの割合がほぼ半々というのは、意図されたものなのでしょうか?
小畑様:
特にそういう訳ではなく、 元々は居宅の患者さんを増やしていきたいと考えていました。
施設からのご紹介は、一度お付き合いが始まると、 その後も継続的に 患者さんが増えたり、 施設職員のかたが 系列 施設へ異動 し 継続してご依頼をいただくケースが多いため、結果的に施設の患者さんの割合が増えてきました。
これは、当院が提供する医療の質への期待に応えられたことで、施設との間に確かな信頼関係が築け、強固な連携ができたからだと考えています 。

写真:高齢患者様宅での在宅医療
開業の背景と在宅医療への想い
船井総研:
ありがとうございます。ご開業の背景、特に在宅医療を中心にご開業されたお考えについてお聞かせいただけますか?
小畑様:
私は研修医を終えた後、大学院に進みました。当時は給料が出なかったのでアルバイトをしていたので すが、その中でたまたま在宅医療に携わる機会がありました。
病院での終末期医療は、状態が悪化すると医療行為がどんどん増え、最後は病院で亡くなるケースが多かったのですが、自宅では点滴や人工呼吸器といった医療が必要なくとも、適切なケアがあれば家族と穏やかに過ごせることを知りました。
当時、在宅医療はまだ一般的ではなかったので、「これからこのような医療が日本に必要になる」と感じ、大学院生の頃からアルバイトは全て在宅医療に切り替えました。
その後、7年ほど在宅クリニックで勤務し、その間に終末期のケアの質の違いや、医療費 の問題意識が深まりました。
医療費の高騰が日本の社会保障制度に与える影響を危惧し、医療政策を学ぶために大学院に行った経緯もあります。その中で、在宅医療こそがその解決策の一つだと確信しました。
また、勤務していた法人では、病院と在宅医療を両方経験し、患者さんを病院から在宅へ、またはその逆へとスムーズに連携させるメリットを感じていました。
しかし、法人内のクリニックによって医療の質にばらつきがある現状を目の当たりにし、質の高い在宅医療を広める必要性を強く感じました。
特に、24時間対応が不十分なクリニックや、質の低 いサービスが高額な管理料で提供されている現状は問題だと感じました。

写真:小児患者様宅での在宅医療
小児在宅医療と外来診療への参入
船井総研:
在宅医療のクリニック展開後、外来のクリニックも開設されていますが、どのような戦略があったのでしょうか?
小畑様:
私の行動は「やるべきことありき」で、経営的な安定はもちろん必要ですが、利益を追求すること自体が目的ではありません。
小児の在宅医療は、 2 年目から始めましたが、数億円の赤字を掘るほど採算が合いませんでした。
しかし、生まれた時から医療的ケアが必要な子や難 病の子どもたち など、最も困っている子どもたちにこそ、社会の資源を投入すべきだという信念があります。
これは、採算度外視で「やる」と決めていました。
私たちが在宅医療で関わるのは、すでに状態が悪化している終末期に近い方々がほとんどです。
しかし、日本全体の医療の質を向上させるには、現役世代の生活習慣病へのアプローチが不可欠だと考えています。
高血圧や糖尿病などで薬を飲むだけでなく、食事や運動指導を通じて根本的な改善を促す医療が、日本の社会全体で当たり前になるべきだと考えています。
現状 、多く のクリニックでは薬を出すだけの医療がほとんどですが、当院の外来 診療では 常に管理栄養士が常駐し、患者さん自身が健康管理をできるよう支援しています。
この分野は小児在宅医療と同様 、現時点では採算が難しいですが、社会にとって非常に重要な医療だと考えています。

写真:地域連携会の様子
外部連携と地域への啓発活動
船井総研:
介護職との連携、 外部向けの企画など、地域への啓発活動にはどの程度注力されていますか?
小畑様:
特に力を入れてきたのは地域での勉強会の開催です。コロナ禍以前の 2016 年から2019 年までは、月に 8 回もの頻度で勉強会を企画していました。各エリアで週に2〜3回開催するようなペースでしたね。
ケアマネジャーさんなど地域の多職種の方々は、医師に対して敷居の高さを感じ、日々のコミュニケーションが取りづらいという声がありました。
そこで、直接医師と話せる場を提供し、顔が見える関係性を築くことを目的としていました。
特に反響が大きかったのは、小児在宅医療に関する勉強会で、外部講師の先生も招き、約80名が参加しました。私自身も多くの勉強会で登壇し、地域の皆さんに顔を覚えていただきました。
医師はコミュニケーションが取りにくいと思われがちですが、直接話すことで「こんな人なんだ」と理解してもらい、安心して依頼してもらえる関係性を築くことができました。
当院が「何でも大丈夫だ」と信頼してもらえるよう、常に質の高い医療 の 提供を心がけています。
今後の展望について
船井総研:
今後の展開についてお聞かせいただけますか?
小畑様:
現在、大宮と赤羽の クリニックは 患者数が 増え、 管理が難しくなってきたため、エリアを分けて新しい拠点を出すことを検討しています。
一部の患者さんを新しい拠点に引き継ぎ、管理をしやすい規模に調整していく予定です。
また、西東京エリアでは、既存の外来クリニックを拠点として、昨年から本格的に在宅医療を始めています。このエリアは、在宅クリニックが 少ないわけではありませんが、ケアの質が不十分で、患者さんがすぐに病院に戻ってしまうケースが多いと病院の先生方がおっしゃっています。そのため、この西東京エリアの在宅医療、特に小児のケアを充実させていきたいと考えています。
船井総研:
本日はご開業から在宅医療への想いや取り組みについてご教示いただきありがとうございました。
小畑様:
こちらこそありがとうございました。
【医療法人社団ときわホームページ】
【医療法人社団ときわ採用情報】
https://tokiwagroup.jp/recruit/
【医療法人社団ときわ X 】
https://x.com/tokiwagroup_?utm_campaign=21812438634
【医療法人社団ときわインスタグラム】
https://www.instagram.com/tokiwagroup_clinic/?utm_campaign=21812438634
無料経営相談のご案内

弊社の病院・クリニック専門コンサルタントが貴院にご訪問、もしくはお客様に弊社までお越し頂き、現在の貴院の経営について無料でご相談いただけます。 無料経営相談は専門コンサルタントが担当させていただきますので、どのようなテーマでもご相談いただけます。
通常、コンサルティングには多大な費用がかかりますが、無料経営相談ではその前に無料で体験していただくことができますので、ぜひご活用いただければ幸いでございます。