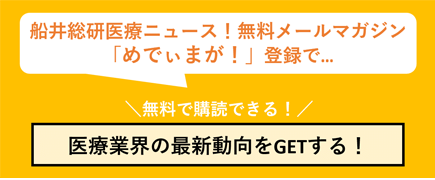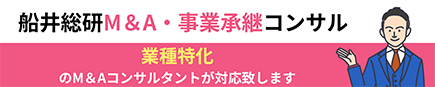医療法人社団オカニューロケアクリニック

医療法人社団 オカニューロケアクリニック 理事長
岡 考(おか こう)様
今回は、静岡県三島市にある「みしま岡クリニック」と「ひいらぎファミリークリニック」を運営されている医療法人社団 オカニューロケアクリニック 理事長 岡 考 様にインタビューをさせていただきました。
本インタビューでは「医療法人社団 オカニューロケアクリニック」が地域医療へ貢献しながら、少子高齢化社会という日本社会が直面する問題に取り組むとともに、持続可能な経営を実現するための多角的な取り組みについて、お話を伺いました。
◆岡先生の医師としてのあゆみと開業のきっかけについて教えてください。
私は脳神経外科専門医として、勤務医時代には静岡県内の病院で脳神経外科の部長を務めるなど、豊富な経験を積んでまいりました。
30代後半を迎え、専門医としてさらなる貢献のあり方を模索する中で、より地域に根差した形で医療を提供したいという思いが強くなり、開業を決意しました。
勤務医時代、部長として一人で多様な症例を診る機会があったため、神経内科領域(認知症を含む)や生活習慣病の管理といった一般内科の領域も経験しました。この幅広い経験から、目の前の患者さんを全人的に診ることの重要性を実感しました。
その思いが、在宅医療を通じて「人々を幸せにする国づくり」に貢献したいというビジョンに繋がっていきました。
◆在宅医療と認知症治療に力を入れるようになったのはなぜですか?
2002年の開業当初は「外来がメイン」のクリニックとしてスタートしました。在宅医療や認知症ケアへ進むきっかけは、開業初年度に特別養護老人ホームの嘱託医を任されたことにあります。特別養護老人ホームは「在宅」とは厳密には異なりますが、この経験を通じて介護を必要とする認知症患者との関わりが増え、認知症ケアの重要性を認識しました。
開業から2〜3年が経ち経営が安定し始めた頃、新たな目標として「認知症」をテーマに掲げました。当時は政府により「高齢者福祉」に関する様々な施策の強化が打ち出され始めた時期であり(ゴールドプラン21等)、認知症という分野が今後重要になると予測したためです。
当時、認知症学会は今と比べると小規模な存在でしたが、認知症専門医制度が創設され、脳神経外科医も資格取得が可能だったため、いちはやく認知症専門医の資格を取得しました。
この認知症専門医としての強みを活かし、特別養護老人ホームやグループホームとの連携を深めることで、在宅医療を拡大していきました。その結果、開業当初は「外来7:在宅3」だった売り上げ比率が、現在では「外来1:在宅8」と大きく逆転し、在宅医療が医療法人の中核事業となっています。
また、当法人には、常勤医師3名、非常勤医師3名、看護師25名、事務職員6名が在籍しており、職員は外来・在宅の両方の業務に携わっています。
◆サービス付き高齢者住宅事業への展開にはどのような意図がありましたか?
認知症のマネジメントは、薬物療法だけでは限界があると感じたためです。当時は新しい認知症治療薬も登場していましたが、その効果は限定的であり、介護という要素が不可欠だと強く感じました。
しかし、それでも「何か足りない」と感じ、「衣食住の一体提供」というビジョンに行き着きました。介護(衣)、栄養(食)、そして住まい(住)を統合的に提供することで、より質の高いケアができると考えたのです。
この考えを具現化したのが、サービス付き高齢者住宅(サ高住)です。これは、高齢者の孤独死や賃貸住宅を借りられない問題に対応するため、当時の政府が推進したモデルでした。当初は入居者が集まらず苦労しましたが、8年ほど経った今では稼働率ほぼ100%で、入居待ちが出るほどの人気です。
このサ高住は、介護度が低い方、あるいは自立している方を主な対象としています。これは、既存の介護サービスでは満たしきれないニーズに応え、高齢者の住まいの選択肢を広げることで、ノーマライゼーションや地域包括ケアの先駆的な役割を果たしたいという意図があります。入居者の方は基本的に介護が必要になるまで長く住み続けられ、介護度が高くなれば提携施設に紹介しています。
◆貴法人の経営理念と今後の展望について教えてください
当法人は現在、成長期を終え、安定期に入った段階だと考えています。今後の事業展開においては、高齢者福祉における課題を深く理解し、それに対応するサービスを提供することを目指しています。
地域における高齢者福祉の課題は「医療」「介護」「移動」の3つに集約されると考えており、これらのニーズを満たす事業展開を大切にしています。
これらのニーズを満たす場所として、三島駅前という立地を非常に重視しています。三島は東海道の宿場町であり、災害リスクも低く、新幹線の駅があるため首都圏からのアクセスも良好です。
また、将来的にはリニア中央新幹線も開通し、さらに首都圏との距離感が短縮されます。都心部での高額な土地取得に比べて、この地域での事業展開は資金的にも現実的です。
こうした背景から、「三島駅を中心としたドミナント戦略」を掲げています。
これは、単に事業を拡大するだけでなく、地域に根差した信頼関係を築き、高品質な医療サービスを提供し続ける、ということを意味します。
◆日本の医療業界の未来と貴法人の戦略について、どのようにお考えですか?
日本は2035年までに大きな医療改革を迫られており、これまで中小病院が担っていた役割を、我々のようなクリニックが担当するようになると考えています。
これに対応するため、当法人では「多機能大規模クリニック」というビジョンを掲げています。CT、MRI、エコー、レントゲンなど、病院並みの設備を備え、これにより、地域住民のあらゆる医療ニーズに対応できる体制を構築しています。
今後の目標は、医師が就職したいと思えるようなポテンシャルのあるクリニックを創ることです。持続可能な医療を提供し、医師が安心してキャリアを築けるようにするためには、外来診療に加えて、在宅医療という軸が重要だと考えています。
外来で認知症の患者さんを診ていくうちに、自宅でのケアが必要になり、それが徐々に広がり、地域からの信頼を得て成長してきました。この信頼関係を非常に大切にしています。
また、国が推進する「かかりつけ制度」は、クリニックが特定の患者さんを登録し、その診療を包括的に担うことで報酬を得る英国スタイルに近いものになると考えています。これにより、多機能で幅広い診療に対応できるクリニックの存在意義がより高まっていくと考えています。
◆最後に、その他の事業展開や経営に関する考えについて教えてください。
現在の日本の状況を考えると、人口減少は避けられず、インフラ整備も困難になっていくでしょう。こうした中で、地域に密着し、医療、介護、住まいを一体的に提供する「コンパクトシティ」的な取り組みが重要だと考えています。
サ高住事業は、公的医療保険や介護保険の公定価格の対象外の事業であり、今後も安定した収益の軸となるでしょう。
また、医療における投資は、単なる損益分岐点を超えるだけでなく、「ワクワクするようなもの」がなければ意味がないと考えています。
長期的な事業計画は、現代のVUCA時代においては難しいと考えており、5年から7年で採算を回収し、ダメなら撤退するという考え方も、リスクを抑える上では有効かもしれません。
私たちは、単なる利益追求ではなく、「人の幸せ」を追求することを仕事の根本に置いています。当院の強みは、「クオリティ、コストパフォーマンス、アクセス」の三拍子が揃っていることです。今後もこの理念を堅持し、地域に貢献していきます。現在の新規患者数は好調に推移しており、私たちがやっていることは大きく間違っていないと確信しています。
高齢者の住まいに関しては、首都圏からの移住者も多く、今後はがんセンターとの連携も含め、治療のために住まいを借りるというニーズも増えていくと考えています。不動産業界の方とも連携し、高齢者の住まいづくりという社会的な課題に貢献していきたいと考えています。
無料経営相談のご案内

弊社の病院・クリニック専門コンサルタントが貴院にご訪問、もしくはお客様に弊社までお越し頂き、現在の貴院の経営について無料でご相談いただけます。 無料経営相談は専門コンサルタントが担当させていただきますので、どのようなテーマでもご相談いただけます。
通常、コンサルティングには多大な費用がかかりますが、無料経営相談ではその前に無料で体験していただくことができますので、ぜひご活用いただければ幸いでございます。